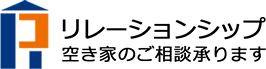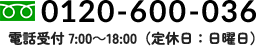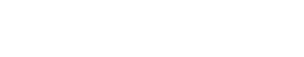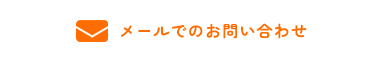遺品整理の第一歩:基本的な手順と始め方を解説2025.07.01

人生の中で避けては通れない「遺品整理」。
しかし、いざ自分がその立場に立つと、
「何から手をつけたらよいのか分からない」
「大切なものと不要なものの判断がつかない」
と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、初めて遺品整理に取り組む方に向けて、基本的な流れや注意点、スムーズに進めるためのポイントを分かりやすく解説します。
「故人の想いを大切にしながら、きちんと整理したい」と考えるすべての方にとって、役立つ第一歩となる内容をお届けします。
遺品整理の基礎知識と始め方
遺品整理は故人の残した品々を整理し、必要に応じて処分や保存、分配を行う作業です。
この作業は感情的な負担が大きいため、効率よく進めるための計画と準備が重要です。
遺品整理をどのように始めるべきか、その基本的な手順と効率的な方法について詳しく解説します。
さらには、家族の協力を得ながら進める際のポイントや、特に重要な書類整理のコツについても触れます。
遺品整理とは?基本的な手順をお伝えします
遺品整理とは、亡くなった方が生前に使っていた品物を整理し、「残すもの」「譲るもの」「処分するもの」を分けていく作業のことです。ただの片づけではなく、故人の想いと向き合いながら行う、心の整理でもあります。
まずは、遺品の量を全体的に把握しましょう。特に大切なもの――たとえば通帳や保険証書、契約書類などの重要な書類を最優先で探し、保管するようにしましょう。これらは後の手続きに必要になることが多いため、見落とさないよう注意が必要です。
次に、家具や衣類、日用品などを種類ごとに分けていきます。何を残し、何を譲るか、どのように処分するか――家族と話し合いながら、ひとつひとつ丁寧に判断していきましょう。複数人で作業することで、思い出を共有したり、客観的な視点で進められたりするメリットもあります。
効率的な遺品整理の始め方と優先順位
はじめに取りかかるのは、書類の整理からがおすすめです。
身の回りの自分でできるところから進めていきましょう。引き出しなどにしまわれている重要書類の見落としがないようにだけ注意しましょう。
次に、家具や家電、大型の不用品についてです。持ち運びが大変だったり、処分方法が特殊なものが多いですので、必ず事前に処分の方法を確認しておきましょう。
自治体で対応できるもの、専門の業者にお願いした方がよいものなどを整理しておくと、当日になって困ることがありません。必要に応じて、不用品回収業者や遺品整理の専門業者に相談するのもひとつの方法です。
また、家族や親族が関わる場合は、あらかじめ役割分担を決めておくことがポイントになります。丁寧さと計画性を持ちながら、無理のない範囲で少しずつ、心の整理も兼ねて進めていきましょう。
遺品整理に必要な準備と心構え
遺品整理は心の準備とともに物理的な準備も大切です。作業に必要な道具やチェックリストを事前に準備し、整理の進捗を把握できるシステムを作りましょう。心構えとしては、感情に流されず、冷静に判断することが求められます。また、思い出の品を無理に捨てる必要はありませんが、将来のことを考え、合理的に決定する力も必要です。遺品整理は一人で抱え込まず、家族の協力を得て進めましょう。
具体的な遺品整理の手順について

遺品整理を行う際は、何から手をつければよいか迷ってしまうことも多いものです。感情と向き合いながら進める作業だからこそ、順序立てて取り組むことが大切です。ここでは、無理なく進められる具体的な手順をご紹介します。
ステップ1:書類・貴重品の整理
まず最初に取りかかりたいのが、書類や貴重品の整理です。通帳や保険証券、遺言書、不動産関連の書類などは、相続や各種手続きに必要となるため、最優先で確認しましょう。見つけたものは種類ごとに分け、ファイルにまとめておくと安心です。印鑑や鍵、貴金属などの貴重品も、保管場所を決めて一か所に集めておきましょう。処分してよいか迷う書類は、無理に捨てずに保留しておくのが安全です。最初に大切なものを整理しておくことで、その後の作業がスムーズになります。
ステップ2:写真・アルバム・形見分け
遺品の中でも、写真やアルバム、故人の愛用品などは、思い出が詰まった大切な品です。処分するか残すかをすぐに決めるのが難しい場合は、無理に判断せず、一時的に保管することをおすすめします。形見分けをする際は、家族や親族と相談しながら、思い出や関係性を大切にして分けましょう。誰がどの品を受け継ぐかを明確にしておくと、後々のトラブルも防げます。感情に向き合う大切な時間でもあるため、焦らず、心の整理とともに進めることが大切です。
ステップ3:自分で使うもの
故人が使っていた日用品の中には、今後ご自身やご家族で使えるものもあるでしょう。衣類、調理器具、文房具など、状態の良いものは再利用の候補になります。ただし、衛生面や使用頻度を考えて、本当に必要かどうかを見極めて選びましょう。感情的になりすぎず、「使う・使わない」「残す・譲る」を基準にして仕分けるとスムーズです。再利用する物は一か所にまとめ、生活の中で無理なく活用できるよう準備しておくと、整理の効果がより実感できます。
ステップ4:家具・家電などの処分
遺品整理の最後のステップとして、家具や家電の処分があります。大型のものは搬出が大変なため、事前に自治体の回収サービスを確認したり、不用品回収業者に依頼する準備をしましょう。まだ使えるものは、リサイクルショップや寄付も検討できます。冷蔵庫や洗濯機など一部の家電は「家電リサイクル法」に基づいた処分が必要ですので、対応方法には注意が必要です。処分に迷う物は一時保管し、家族と相談しながら最終判断をすると安心です。
遺品整理の進め方と手順をお伝えします

遺品整理は、通常の整理整頓とは異なり、故人を偲ぶ特別な意味を持つ作業です。そのため、丁寧に進めることが求められます。本記事では、遺品整理における基本的な手順を説明し、効率良く進めるための方法を解説します。これにより、無理なく計画的に進めることができるでしょう。これから始める際の参考にしてください。
手順1: 計画を立てましょう
遺品整理を始める前に、まず計画を立てることが重要です。計画を立てる際は、全体のスケジュールを設け、家族と協力し合える時間を確認しましょう。時間が許す範囲で、各日ごとに何を行うのか具体的に書き出しておくと、作業がスムーズに進みます。また、書類整理などの優先順位もこの段階で決めておくと効率良い方法で進められます。準備が整うことで、心に余裕を持って作業に集中できるようになります。
手順2: 大まかなカテゴリーに分けてみましょう
効率的に遺品整理を進めるためには、物の分類が不可欠です。まず、遺品を大まかに「残しておくもの」「処分するもの」「家族で話し合うべきもの」に分けます。家具や家電、大量の不用品についても、カテゴリーごとに分けることでそれぞれの処分方法を考えやすくなります。また、感情的な判断を避けるため、冷静に整理を進める手助けになります。このステップが、後の具体的な作業の準備段階となり、優先順位を明確にします。
手順3: 具体的な作業を進めましょう
カテゴリー分けが終わったら、次は実際の作業に入ります。まず重要なもの、特に書類整理については、一つ一つ確認しながら進めましょう。優先順位を決めて、順序立てて作業することで無駄を減らせます。また、家具の処分方法についても事前に確認し、適切な業者を選ぶと手間が省けます。家族との協力も重要なので、協力を仰ぎながら進めましょう。この時点でのチェックリストが後の確認を容易にします。
手順4: 最後に確認と整頓
すべての作業が終わったら、最後に確認と整頓を行います。ここでは、持ち物チェックリストに基づき、必要なものが揃っているかや、忘れ物がないかを確認します。書類整理が完了しているかの最終チェックも忘れずに行いましょう。整理が完了した場所を見渡し、改めて整頓されているかどうかを再確認し、必要であれば微調整します。このように細部まで確認することで、遺品整理全体が完了し、安心して締めくくることができます。
まとめ:遺品整理を依頼するなら株式会社リレーションシップがおススメ
遺品整理は、故人の想いを大切にしながら行う、とてもデリケートな作業です。
しかし、心身への負担が大きく、ご遺族だけで行うには限界があります。「どこから手を付けてよいか分からない」「時間が取れない」「専門的な処分が必要」——そんなときこそ、プロの力を借りることが重要です。
神奈川県を中心に対応している株式会社リレーションシップは、横浜市・川崎市・藤沢市・小田原市など、県内広域で多数の実績を持つ遺品整理の専門業者です。
当社には遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍しており、法令を守りつつ、丁寧かつ迅速な対応を行います。
さらにリレーションシップでは、遺品整理だけでなく、ハウスクリーニング・ゴミ屋敷の清掃・不動産売却・解体工事までワンストップで対応可能です。
「片付けた後、家をどうすればいいかわからない」というお悩みにも、包括的なサポートをご提供。複数の業者に依頼する必要がないため、手間や費用を大幅に削減できます。
無料見積もり・現地調査も柔軟に対応しており、ご相談はお電話・メールでいつでも可能です。
「大切な遺品を信頼できる業者に任せたい」とお考えの方は、ぜひ一度リレーションシップへお問い合わせください。心を込めてサポートさせていただきます。